社会の超高齢化に伴い相続ビジネスが盛んです。しかし、税理士や弁護士さんに「早めの相続対策が大切です」と言われても「所詮、あなたの仕事につながるのでしょう」と思えてしまうかもしれません。そのため、大切なことと分かっていても相続対策は先延ばしになりがちです。
しかし、遺言書は相続の対策として残され相続人にも、またご自身の財産管理や残された方々へのメッセージとしてとても意義のあるものです。ですから、認知症となる前に遺言を残しておくべきなのです。
ところが、遺言書を残される方が高齢で認知症であったり、また判断能力が低下していて認知症の疑いがある場合は、どのように遺言書を残したら良いのでしょうか。
さらに認知症を発症していなくとも、「ぜひ書いておいたほうが良いのでは」と思うケースもいろいろあります。
そこで今回の記事では、裁判で遺言能力鑑定を行なったことがある認知症専門医として、また自身でも45歳で遺言を書き記した長谷川嘉哉が「認知症と遺言」についてご紹介します。
目次
1.遺言作成能力とは?
遺言書を残すことができるのは、遺言作成能力がある人となります。遺言作成能力とは「遺言書を残すことができる人は最低限このような能力がある人ですよ」というものです。しかし、「遺言能力が実際にどの程度なのか」は、実は明確に基準を示すことが困難な場合が多いのです。
1-1.民法における遺言能力の規定
民法の上では遺言能力に関する決まりが以下のように示されています。
- 「15歳に達した者は遺言をすることができる。」(民法961条)
- 「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(民法963条)
-
※「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」(民法973条②)
この二つの条文を読むと「15歳以上であれば遺言書を残せる」と読み取れます。法律の上では未成年者でも15歳を過ぎれば遺言能力があるため、かなり広い範囲で認められていることとなります。また、判断能力などにハンデキャップがある人に対しては成年被後見人の場合だけ規定があります。それ以外には遺言書を作成するためには特に制限がないと考えてよさそうです。
1-2.判例や学説の遺言能力
上記のように民法上では基本的な遺言能力についての条文は二つしかありません。しかし、この二つを満たしていてる人が遺言書を残しても、その遺言書が無効であるとの判決が出された裁判が多数あります。この事実より、判例や学説での遺言能力は以下のようになるといわれています。
- 遺言書の内容やその法律効果を理解し判断することができるかどうか。
- 認知症などを患っていたら、遺言執筆当時の認知症の症状はどの程度であったか。
判例や学説での遺言能力の基準はたった上記2項で示されるような単純な物ではありませんが、民法上の条文で示されている内容と比べると、遺言の能力があるかないかを総合的に厳しく判断していることがわかります。
2.認知症と診断されていても有効な場合もある
実は、認知症の症状は多彩であり病状は様々です。持っている財産や相続人によって遺言の内容も変わります。そのため、「認知症である」と診断されている場合でも、認知症の症状が軽度であり、本人が自分の行為の結果を判断できるだけのしっかりとした遺言能力がある時に遺言書が作成されたと証明できれば、遺言書は無効とはなりません。もちろん、そのような内容の医師の診断書や詳細なカルテが必要にはなります。
2-1.公正証書遺言が無効とされた例:横浜地裁平成18年9月15日判決
長谷川式評価スケールでの点数は9点あったという事例です。
- 遺言作成時点でアルツハイマー性認知症と診断されていたこと
- 遺言の内容が比較的複雑だったこと(遺産の一部のみを共同で相続させる、遺言執行者を複数人指定するなど)
- 遺言作成時、公証人が遺言内容を読み上げたものに対して「はい」などという簡単な肯定の言葉しか口にしなかったこと
などから、遺言能力はなかったと判断し、遺言は無効とした判例。遺言があまりに複雑な内容のため、無効と判断されたようです。裁判では認知症のレベル・症状だけではなく総合的に判断しているのです。
2-2.さらに進んだ認知症でも遺言が有効とされた例:京都地裁平成13年10月10日判決
しかし、長谷川式評価スケールでの点数は4点と低かったものの、「遺言の内容が簡単なものであったこと」「病院の看護日誌から看護師と会話ができていたことが認定されたこと」などから、遺言が有効であると認めた判例があります。
実際、評価スケール4点で遺言作成が有効とされたことは専門医としては驚きですが、遺言の内容が相当に簡単ものであったと予想されます。
例えば、「自分の財産は全て妻に渡す」とだけ書いてある場合などは、認められる可能性があるといえます。

3.執筆時に「認知症と診断されなかった」場合は、遺言は原則として有効
認知症と疑われた場合の、判例には有効、無効それぞれの判例がありました。しかし、認知症ではない方であれば、遺言は有効になります。そのため、必須ではありませんが、認知症専門医の診察を受けて、「認知症ではない」という診断書をもらってからの遺言作成は相当に信憑性が高まると思われます。
4.一時的な入院中に執筆した遺言は無効になる可能性がある
最近、相続に絡んだ遺言作成の際の患者さんの意志能力の有無の相談をよく受けます。もちろん専門である認知症については、その認知機能の評価で意志能力の有無を証明する事は可能です。しかし、皆さんが理解されていないことの一つに、“認知症と意識障害は違う”ということがあります。
言葉の定義では、認知症とは『後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態』であり、意識障害とは、『物事を正しく理解することや、周囲の刺激に対する適切な反応が損なわれている状態』です。ある意味、認知症は数日で急激に悪化することはありませんが、意識障害は数時間で発症することがあります。
例えば、肺炎で高熱になったり、心不全で全身の循環が悪化すれば、意識障害が引き起こされます。しかしこれは認知症になったわけではありません。このようなケースでは、仮に認知症でなくても、意識障害時の遺言作成は無効です。
先日相談されたケースでは、『肺炎で入院中の遺言作成が有効であるか?』でした。入院中、一過性に状態が良くても、入院期間であれば、意識レベルが問題ないと言い切ることは困難です。そのため、入院中の遺言作成は無効です。それにもかかわらず、入院中の患者さんの傍に立会人2名が出向いて、公正証書遺言を作成させていました。立会人の見識も疑われますし、契約自体無効です。
今後、相続に伴う遺言作成の事案は増加が予想されます。法律の現場に対して、医療側も明確な意見を述べていく必要があります。
5.私が経験した遺言無効裁判の実例
私は遺言無効裁判の鑑定を依頼されたことがあります。故人の遺言書に対して二人の息子さんが、「有効である」という方と、「遺言作成時には意志能力はなく無効」と主張する方で意見が対立したのです。

5-1.鑑定する医師同士の意見の違い
争点は、遺言作成時の意志能力です。遺言者は、数か月にわたって高カロリー輸液のみの管理。遺言作成の前日にも、夜間不穏に対して抗精神病薬の注射が行われている点がありました。これらを検討して、私は遺言作成能力はないと判断しました。内科医としては、極めて常識的な判断をしたつもりでした。しかし、相手方の精神科医の鑑定は遺言作成能力はあると主張したのです。つまり、医師同士であっても真っ向から意見が対立したのです。
5-2.裁判所の判断
しかし、過去の話の議論でしかありませんし、神経内科専門医と精神科専門医の意見が分かれては、裁判所も白黒をつけることはできません。結果的には結論は出ず、双方で落としどころを見つけ示談で終了しました。
5-3.家族関係の崩壊
裁判的には、解決したわけですが、遺族の間で裁判が起こった場合、関係の修復は不可能になります。私自身は、「最高の先祖の供養は、残された家族が仲良く過ごすことである」と教えられました。そのためにも遺言作成能力があるうちに適切な遺言を作成して遺族の争いを避けるべきなのです。
6.高齢者が遺言書を残すときの3つの注意点
高齢の方が遺言書を残す場合には後からのトラブルとならないよう、遺言書作成のの時点で以下のようなことに気をつけましょう。
6-1.公正証書遺言で残す
自分でつくる自筆証書遺言は秘密裏に作成することができますが、法的要件不足などで無効となってしまう可能性があります。そのため、遺言書の法的要件に関して安心ができる公正証書遺言での作成を行いましょう。公正証書遺言であれば公証人が作成し証人の立ち会いもありますので、より信頼できる遺言書となります。もちろん私も公正証書遺言を作成しました。
6-2.医師の診断を受ける
公証人は医師ではなく、遺言者の判断能力の有無までは確定できません。もし遺言能力に不安がある方は、認知症専門医にて診断書を作成することが良いでしょう。当院では、初診の段階で契約能力がない場合は、診断書に「契約能力はない」ことを記載しています。実際に、当院初診時に「契約能力がない」と診断されたにも拘らず売買契約を行い、無効になったこともあります。(その際、弁護士さんにも、初診時に契約能力の有無をご家族に紙に書いてお渡ししていることに驚かれましたが・・)
6-3.医師の診断書が絶対ではないが、うまく使おう
できれば上記した通り、遺言書の作成時に「遺言作成能力に問題がない診断書」を取得することが良いでしょう。
ところが専門医であっても遺言作成能力の知識がなく、みなさんの方で「遺言書作成能力の診断書を作ってください」とお願いしても対応してもらえないことも多いでしょう。遺言に必ず必要な書類ということでもありません。
医師は認知症を医学的に診断しますが、遺言能力は法的に判断されるものです。診断書はあくまで参考資料の一つになります。遺言書の作成において診断書の取得は必須ではありませんので、状況に応じて診断書を活用する必要があります。
7.絶対に遺言を残すべきと感じた経験とは
認知症の外来をやっているだけでも、このケースは「絶対に遺言が必要」と思われるケースがあります。
7-1. 介護しているお嫁さんにも…と思ったケース
在宅診療をしていると、実の子供さんは殆ど介護に関与せず、ご長男のお嫁さんが一手に介護を担っているケースがあります。ときに、ご長男さんはすでに亡くなっているのに、お嫁さんが気丈に義理の親の介護をしていることがあるのです。この場合、遺言がなければ義理の親が死んだときには、お嫁さんは何も相続を受けることができません。何もしてこなかった実子にのみ相続されるのです。例えば、相続によって介護していた親の家を売却して実子が分配したため、お嫁さんは住む場所さえ失ったケースがあります。できれば健気なお嫁さんに、遺言で財産を残してあげてほしいものです。
7-2.高齢者夫婦で、子供がいなかったケース
子供さんがいない夫婦の場合、配偶者が無くなったときに、一部の相続権が兄弟にも発生します。例えば、夫婦二人でマンション生活をしており、ご主人が死亡後、兄弟から相続財産の一部を要求され、マンションを売ることになったケースもあります。遺言で一言「全財産を配偶者に譲る」と書いておくだけで解決したのです。
*法定相続人が最低限の遺産相続分を取得できる遺留分の権利は、兄弟・姉妹には認められていません。遺言で「100%配偶者に譲る」ですべて解決するのです。
7-3.内縁関係の夫婦のケース
最近、外来をやっていると入籍をしていないカップルが増えています。ある程度の年齢になって配偶者を失くした男女が、再び結婚をする。しかし、それぞれの子供や財産のことから、籍は入れないような「事実婚」になるようです。超高齢化の時代、事実婚も長期になります。その結果、長年の事実婚後、亡くなるケースがあるのです。この場合、遺言がないと長年一緒に暮らしてくれた相手に財産を残してあげることができません。
私は以前にも事実婚の男性の遺言作成能力について診断を依頼されたことがあります。何とか可能性を探ったのですが、あまりに認知機能障害が進行しており、遺言作成は有効と診断できなかったのです。事実婚の場合は、双方が元気なうちに遺言で財産の一部を残してあげてほしいものです。

8.まとめ
- 認知症になったら、絶対に遺言が書けないわけではありません。
- 医師の診断書は、あくまで法的な遺言作成能力の可否の判断の一つです。
- やはり、認知症でないうちの遺言作成が最も安全で有効です。
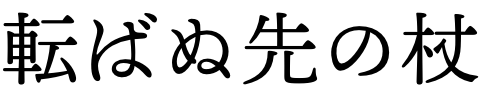


 認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。
認知症専門医として毎月1,000人の患者さんを外来診療する長谷川嘉哉。長年の経験と知識、最新の研究結果を元にした「認知症予防」のレポートPDFを無料で差し上げています。